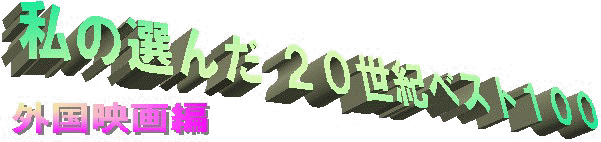
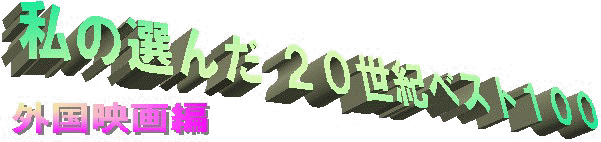
| PART 1 (No.1〜20) |
|
お待たせしました。「日本映画編」に引き続いて、「私の選んだ20世紀ベスト100・外国映画編」をお届けします。 |
| No | ベ ス ト 作 品 | ご 参 考 |
| 1 |
「キッド」 ('21) 米/監督:チャールズ・チャップリン 1本目は何にしようか、いろいろ考えた。双葉さんのように、メリエスの「月世界旅行」も候補に挙げたが(結構楽しくて私は好き)、何分にも10分ほどの短編であるので除外。で、やっぱりチャップリンということに…。チャップリンはいわゆるドタバタ・コメディからスタートし、次第にペーソスや社会批判を盛り込んだ、優れたな映画を作るようになる。この作品は初めての長編であり、コメディでありながら泣かされ、感動させられた。これは学生時代、無声映画鑑賞会で、弁士のナマの活弁付きで観ている。 |
双葉さんのベスト100: (1)「月世界旅行」 ('02 監督:ジョルジュ・ メリエス) (2)「大列車強盗」 ('03 監督:エドウィン・S・ ポーター) (3)「國民の創生」 ('15 監督:D・W・グリフィス) (4)「カリガリ博士」 ('19 監督:ロベルト・ヴィーネ) (5)「キッド」 (左参照)
|
| 2 |
「チャップリンの黄金狂時代」 ('25) 米/監督:チャールズ・チャップリン
|
双葉さんのベスト100:
(6)「ドクトル・マブゼ」 ('22 監督:フリッツ・ラング) (7)「幌馬車」 ('23 監督:ジェームズ・ クルーズ) (8)「結婚哲学」 ('24 監督:エルンスト・ ルビッチ) (9)「アイアン・ホース」 ('24 監督:ジョン・フォード) (10)「チャップリンの黄金狂時代」 (左参照)
小林さんのベスト100: |
| 3 |
「戦艦ポチョムキン」 ('25) ソ連/監督:セルゲイ・エイゼンシュテイン これはわが国では戦後もずっと公開されず、ようやく'67年になってATG(アート・シアター)で正式公開され、私は今は無きATG北野シネマで観ている。エイゼンシュテイン監督のいわゆる“モンタージュ理論”が開花した作品として知られるが、私は単にスリリングなスペクタクル・アクションのお手本として楽しめた。凄いのは有名な“オデッサの階段”のシークェンスで、銃を乱射する兵士達と逃げ惑う群衆とをカットバックで繋ぎ、そしてイメージショットや階段を落ちて行く乳母車等の映像を巧みにインサートした編集(モンタージュ)のうまさで、今ならさして特異でもないこうした編集テクニックをこの時代に最初に編み出したというのが凄い。そして今見てもこのシークェンスのスリルとダイナミズムは決して古臭くない。そして無名の素人役者ばかりを使った、ドキュメンタリー的なタッチも新鮮である。まだ古い洋画をそれほど観ていない時期に観た…というのも幸いしているのだろうが、とにかく私にとっては強烈な印象を残している、歴史的名作である。なお乳母車が階段を落ちるシーンはブライアン・デ・パルマが「アンタッチャブル」でまるごと再現し、これもニヤリとさせられた。…それにしても、もっと古い作品だと思っていたのだが、こうやって並べて見ると、チャップリンの「黄金狂時代」やバンツマの「雄呂血」と同じ年の作品だったのですね。(日本公開'67年) |
双葉さんのベスト100:
(11)「ビッグ・パレード」 ('25 監督:キング・ヴィダー) (12)「戦艦ポチョムキン」 (左参照)
*「メトロポリス」(27)。フリッツ・ラング監督のSF映画の古典。サイレント。金色のロボット・マリアは「スター・ウォーズ」のC−3POの原型か。後年、ジョルジョ・モローダーが音楽をつけたサウンド版が製作されたが、余計なお世話の気がする。音のないオリジナル版でも十分面白い。 |
| 4 |
「キートン将軍」 ('26) 米/監督:バスター・キートン/クライド・ブルックマン バスター・キートンも私の好きな俳優である。体を張ったアクションとシュールなギャグ(浮き輪が沈んで錨が浮く…という「蒸気船」の不思議なギャグもキートンなら納得(笑))には大笑いさせられた。この作品以外にも好きな作品はいっぱいあるが(1.「キッド」の欄外参照)、キリがないのでこの作品に代表させていただく。南北戦争を舞台とした、スケール大きな作品で、次々とつるべ撃ちに飛び出すギャグとスペクタクル・アクションの洪水に理屈抜きに楽しませてもらった(本物の列車が川に転落するアクションにはびっくりさせられる)。チャップリンと違って、“泣かせ”も“人情味”もない為評価は意外に低いが、キートンの乾いた笑いとシュールで不条理なギャグ、そして体力の限界に挑戦するかの如きスタント・アクションは、多分誰もマネできない独特の味である。ジャッキー・チェンがいろいろな作品でオマージュを捧げているのも分かる気がする。なおビデオでは「キートンの列車大追跡」「キートンの大列車強盗」など、いろんな題名で出ているので気をつけられたし。(日本公開'26年) |
双葉さんのベスト100:
(13)「アッシャー家の末裔」 ('28 監督:ジャン・エプスタン) (14)「ラヴ・パレイド」 ('29 監督:エルンスト・ルビッチ)
*ルイス・ブニュエル監督の「アンダルシアの犬」(28)は悪夢のようなシーンだけが続く、いわゆるアバンギャルド作品。女の目玉をカミソリで裂くシーンはショック。しかし捨て難い味がある。 |
| 5 |
「会議は踊る」 ('31) 独/監督:エリック・シャレル ここから後はトーキー作品。ドイツ映画と言えば何となく硬いようなイメージがあるうえ、ストーリーだけ聞けば“ナポレオン失脚後の欧州の情勢に対処する1814年のウィーン会議”という史実がテーマであるというので、難しい作品では…と思ってしまうが、観たら誰もびっくり。なんとまあ楽しいシネ・オペレッタの快作である。ウィーン会議にやって来たロシア皇帝アレクサンダー1世(ヴィリー・フリッチュ)と、地元の手袋屋の娘(リリアン・ハーヴェイ)との恋模様を中心に、なんとかアレクサンダーを出席させまいと企む宰相メッテルニヒと、それを出し抜き替え玉(フリッチュ二役)を使って翻弄するアレクサンダーとの駆け引きが実に楽しいし、随所にトボけたコミカルな味わいがあってほのぼのとさせられる。そして極めつけは、アレクサンダーに招かれ、彼の別邸に馬車で向かう途中にリリアン・ハーヴェイが嬉しさのあまり「ただ一度だけ」を歌い出だすシークェンスで、ここはシネ・オペレッタとしての楽しさが爆発する映画史に名高い名シーン。ほとんどワンカットで馬車が進む間に、町行く人、兵士、そして動物たちまでが祝福しているかのようでとてもハッピーな気分にさせられる。本当に涙が出て来るくらい素敵なシーンで、ハーヴェイならずともいつまでも続いていて欲しいと願いたくなる。気分が落ち込んでいる時にも、このシーンを観れば絶対元気になれる、そんな素敵な作品である。(日本公開'34年) |
双葉さんのベスト100:
小林さんのベスト100:
*「巴里の屋根の下」(30)、「巴里祭」(32)はいずれもルネ・クレール監督の秀作。ただ今から見るとちょっと古めかしい。「巴里の屋根の下」のラストの歌声が延々と流れるシーンは好きなのですがね。 |
| 6 |
「街の灯」 ('31) 米/監督:チャールズ・チャップリン またまたチャップリン。既にトーキー時代になっているにも係らず、チャップリンはこの後もしばらくはサイレント(実はサウンド版)にこだわり続ける。物語は、例によって浮浪者のチャップリンが、街角で花を売っている盲目の貧しい娘(ヴァージニア・チェリル)に恋をし、彼女の目を治す為に、金を稼ごうと奮闘する…というもので、自分も貧しいのに、可哀相な娘の為に献身的な愛情を注ぐ、「キッド」から後の「ライムライト」にまで繋がる“無垢の人間愛”に心が打たれる。効果音と音楽のみで、セリフをまったく喋らない(サイレント映画そのままに字幕がインサートされる)が、これはパントマイムから出発したチャップリンらしい反骨精神の表れでもあるのだろう。彼の努力で娘は手術を受けられることになるが、チャップリンは誤解から警察に捕まり、刑務所に入れられてしまう。そして月日が経ち、二人が再会するラストは、何度見ても泣けてしまう。素晴らしい愛の傑作である。 |
双葉さんのベスト100:
(19)「街の灯」 (左参照) (20)「自由を我等に」 ('31 監督:ルネ・クレール) (21)「暗黒街の顔役」 ('32 監督:ハワード・ホークス) (22)「巴里祭」 ('32 監督:ルネ・クレール) (23)「仮面の米国」 ('32 監督:マーヴィン・ルロイ) (24)「グランド・ホテル」 ('32 監督:エドムンド・ グールディング)
小林さんのベスト100: *チャップリンはあと、「サーカス」(28)もいい。ギャグ満載だがラストはちょっぴり哀愁味がある。 |
| 7 |
「キング・コング」 ('33) 米/監督:メリアン・C・クーパー/アーネスト・B・シュドサック いわゆる怪獣映画の古典。南方の島で発見した巨大猿を興行師(ロバート・アームストロング)がニューヨークに持ち帰り、見世物にするが、美女(フェイ・レイ)に見とれたコングが鎖を引きちぎり、美女をさらってエンパイア・ステート・ビルによじ登る…という物語で、当時としては画期的な特殊効果を駆使して大成功を収めた。私はこれを小学生の頃劇場で観ているが、コングが恐竜と壮絶な格闘を繰り広げたり、高い柵を怪力でぶち破って現れたりするシーンは後に見直しても鮮明に覚えていたくらいである(と言うより、当時は小便チビリそうなくらい怖かったのである(笑))。わが「ゴジラ」と並んで、子供心に強烈なインパクトを与えてくれた点で忘れられない作品である。ラストは飛行機からの機関銃に撃たれ、美女をそっと降ろしてビルから落下して行くコングの姿が悲壮感たっぷりに描かれ、大人になって見直してみれば、これは美女を愛した野獣の哀しいラブ・ストーリーにもなっていた事に気付いた。 |
双葉さんのベスト100:
小林さんのベスト100: |
| 8 |
「モダン・タイムス」 ('36) 米/監督:チャールズ・チャップリン 「街の灯」から5年後の作品。にもかかわらずチャップリンは未だにサイレント映画にこだわっていた。相変わらずの字幕入りサウンド版スタイル(ただし巨大テレビ・スクリーンで監視する資本家はちゃんと喋っている)。前半で特に凄いのは、通勤ラッシュで電車から吐き出されるサラリーマン群を羊の群れとダブらせたり、ベルトコンベアに乗せられた部品のネジを締め続けているうちに、頭がおかしくなって丸いものを見るとレンチで締めてしまう…というギャグ。最初は笑っていても、やがて背筋が寒くなって来る。これは後の高度成長時代、ストレスから神経症になる人間が増えているという、管理社会の弊害をズバリ予言しているわけで、日本で言えば昭和11年…この時代にすでにこんな映画を作っていた事に驚愕する。資本家がテレビ・モニターで監視しているシーンも、今見れば何という事もないが、当時はまだテレビもなかった頃。しかもそれを監視モニターとして利用するという発想をこの時代、既に思いついていたというのが凄い。チャップリンは本当に信じられない天才である。 |
双葉さんのベスト100:
|
| 9 |
「望郷」 ('37) 仏/監督:ジュリアン・デュヴィヴィエ 今さら言うまでもない、ジャン・ギャバン主演の名作中の名作。アルジェリア・カスバに潜伏しているペペ・ル・モコ(ジャン・ギャバン。これが原題)の、故国パリに対する望郷の念。そしてパリからやって来た美しい女ギャビー(ミレーユ・バラン)に惚れ、船に乗って帰るギャビーを見送る為、危険を冒してカスバを出てしまうペペの切ない想い。犯罪映画でありながらメロドラマの傑作にもなっている所が見事。迷路のようなカスバのエキゾチックな情景も印象的。ジュリアン・デュヴィヴィエ作品の中では一番好きである。ラスト、警察に捕まり、警部のお情けで見送りは許されたのに、「ギャビー!」と叫んだ声が汽笛にかき消されるシーンは伝説的に有名。演技、演出、カメラワークいずれも申し分なし。日本人好みのこの映画は、後に「カサブランカ」と並んで多くの日本映画に翻案・リスペクトされる事となる。舛田利雄監督は余程この作品が気に入っているようで、「赤い波止場」「紅の流れ星」「さらば掟」と自身で3度も翻案映画化。他にラストシーンだけなら東映の降旗康男監督「地獄の掟に明日はない」にも巧妙に取り入れられている。(日本公開'39年) |
双葉さんのベスト100:
(33)「舞踏会の手帖」 ('37 監督:ジュリアン・ デュヴィヴィエ) (34)「望郷」 (左参照) 小林さんのベスト100: (18)「新婚道中記」 ('37 監督:レオ・マッケリー) (19)「明日は来らず」 ('37 監督:レオ・マッケリー) (20)「舞踏会の手帖」 *ヒッチコックの「暗殺者の家」(34)は初期の傑作。後の「知りすぎていた男」はこれの自身によるリメイク。同じくヒッチの「第3逃亡者」(37)は濡れ衣を着せられ、追われつつ真犯人を追う…というお得意のパターンによる最初の成功作。建物の外から舞台の奥のドラマーの眼のアップまでをカメラがワンカットで追った移動撮影が見どころ。 |
| 10 |
「大いなる幻影」 ('37) 仏/監督:ジャン・ルノワール 第一次大戦を舞台にした、反戦映画の傑作。ジャン・ギャバンが主役のようになっているが、貴族の誇りを持つボアルデュ大尉(ピエール・フレネー)、裕福なユダヤ人中尉ローゼンタール(マルセル・ダリオ)、そしてドイツ軍収容所長ラウフェンシュタイン大尉(エリッヒ・フォン・シュトロハイム)などの多彩な人物が絡む群像劇とでも言うべきである。面白いのは前半の、収容所内で地下に穴を掘って脱走計画を立てるエピソードで、後の第2次大戦のやはり収容所脱走もの「大脱走」(ジョン・スタージェス監督)と脱走方法・プロセスがよく似ている点である。第一次大戦でも既にそんな作戦があったのだとしたら興味深い話である。 |
双葉さんのベスト100: (35)「大いなる幻影」 (左参照) 小林さんのベスト100: (21)「大いなる幻影」 (左参照)
|
| 11 |
「白雪姫」 ('37) 米/監督:デヴィッド・ハンド ウォルト・ディズニーによる初のカラー長編アニメ。この作品は小学生時代に学校鑑賞か何かで観ており、その鮮やかなカラーと七人の小人のキャラクターの楽しさに夢中になった。以後も何度かリバイバルの度に観ており、さらに子供が幼稚園の頃の再映でまた、今度は子供と一緒に鑑賞するなど、私にとっては個人的にも思い入れが深い作品である。これが世界最初のカラー長編アニメとは思えない程、動きは滑らかでギャグも楽しく、さらに「いつか王子様が」「ハイ、ホー」などの主題歌も素晴らしい出来で、何度観ても飽きない。まだこの時代(昭和12年ですよ!)、カラー技術も開発途上にあったはずで、にも係らず見事な色彩設計で、まったく古さを感じさせない。よく見直してみれば、ミュージカル、ファンタジー、ホラー(女王が変身した魔女が凄くコワい)、サスペンス(小人対魔女の追っかけ)、そしてラブ・ストーリー…と、あらゆるエンタティンメントの要素が詰まっているのにも感心する。古典でありながら永遠に新鮮な、アニメ史上に残る傑作である。(日本公開'50年) |
*ベストに入れられなかったW・ディズニー作品をいくつか挙げておきます。無論全部カラー!作品。 「ピノキオ」(40)。これは誰でも知っているでしょう。主題歌「星に願いを」はあまりにも有名。もっと新しい時代だと思っていたのだが、なんと「白雪姫」に続く長編アニメの第2作だったのですね。しかしまったく古さを感じさせない、永遠の名作です。 「ダンボ」(41)長編アニメ第4作。大きな耳の小象ダンボが、最後高いポールの上から飛び降り、空を飛べるようになるクライマックスにはゾクゾクした。これも小学校の頃学校の団体鑑賞で観ている。 「バンビ」(42)。映像がとても美しい。手塚治虫はこれを劇場で封切期間中毎日、初回から最終回まで観続けていたという。恐らく手塚の「ジャングル大帝」の原型になったのではないか。私も好きな作品です。 |
| 12 |
「バルカン超特急」 ('38) 英/監督:アルフレッド・ヒッチコック
|
小林さんのベスト100: (22)「バルカン超特急」 (左参照) *「民族の祭典」、「美の祭典」(38)。'36年のベルリン・オリンピックの記録映画。レニ・リーフェンシュタール監督が、部分的にヤラセ、別撮りシーンなども取り入れ、さらに望遠レンズや移動撮影などの映像テクニックも駆使して、当時としては画期的な記録映画の傑作を完成させた。今観てもほとんど古さを感じさせない、イマジネーション豊かな映像に感心させられる。 |
| 13 |
「風と共に去りぬ」 ('39) 米/監督:ヴィクター・フレミング これも説明は不要だろう。戦後、何度もリバイバル公開され、その都度客を集めている、不朽の名作。私も数回劇場で観ているが、うち一度はなんと!70ミリ・ワイドスクリーン版であった。元はスタンダード・サイズなので、当然上下がカットされ、クラーク・ゲイブルの頭がチョン切れる等、観辛いことこの上ない。まあ迫力は確かにありましたがね。 |
双葉さんのベスト100:
(36)「風と共に去りぬ」 (左参照) 小林さんのベスト100: (23)「天国二人道中」 ('39 監督:A・エドワード・ サザーランド) (24)「大平原」 ('39 監督:セシル・B・デミル) (25)「ニノチカ」 ('39 監督:エルンスト・ ルビッチ) *「風と共に−」のヴィクター・フレミング監督が同じ年に発表した「オズの魔法使い」(39)も好きな作品。ジュディ・ガーランドが可愛い。現実世界がモノクロで、夢の世界に入った途端に鮮やかなカラーになるのがハッとさせられる。とにかく楽しい。落ち込んでいる時元気になれる作品の1本として推奨したい。 |
| 14 |
「駅馬車」 ('39) 米/監督:ジョン・フォード これも文句なしの名作。アクション映画としても申し分ない出来で、クライマックスのインディアンの襲撃シーンは、そのカメラワーク、カット割り、スタントの凄さ(名手ヤキマ・カヌットが担当)、どれをとっても芸術の域にまで達している。アクションを芸術にまで昇華させた監督はこのジョン・フォードと黒澤明くらいではないだろうか。 |
双葉さんのベスト100:
(37)「駅馬車」 (左参照)
小林さんのベスト100:
|
| 15 |
「スミス都へ行く」 ('39) 米/監督:フランク・キャプラ フランク・キャプラ監督の代表作。「オペラ・ハット」で既に理想主義をテーマに打ち出していたが、本作はさらにそれを押し進め、“政治家の理想像とはどうあるべきか”という難しい題材に挑戦し、そして見事な傑作に仕上げた。ちなみに「オペラ・ハット」の原題は"Mr.
Deeds Goes to Town"であり、「スミス都へ行く」はその姉妹篇である事が題名からも分かるようになっている。 |
双葉さんのベスト100:
(38)「スミス都へ行く」 (左参照)
小林さんのベスト100:
*この1939年は、アメリカ映画に映画史に残る傑作が輩出した年として記憶に留めたい。既出の「風と共に去りぬ」「オズの魔法使い」「駅馬車」「嵐が丘」「スミス都へ行く」等の他に、セシル・B・デミル監督の西部劇「大平原」(39)も挙げておきたい。西部まで鉄道を敷設する男たちの苦難を描く。バーバラ・スタンウィックが男勝りだが、女らしい一面も持つヒロインを好演。デミルらしい派手な特撮もあるが今から見るとややチャチ。なお冒頭のクレジット・タイトルが線路に沿って向こうへ流れて行くスタイルは、ジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」に取り入れた事でも有名。 |
| 16 |
「ファンタジア」 ('40) 米/監督:ベン・シャープスティン ディズニーの実験的アニメの傑作。これも子供の頃観ている。…しかし、これは子供にはちょっと難しい。音楽はクラシックの名曲ばかり、映像もかなり抽象的なものもあったりで、唯一ミッキー・マウスが登場する「魔法使いの弟子」のみ記憶に残っていた。大人になって見直して、はじめて感動した。 |
小林さんのベスト100: (28)「旅路の果て」 ('39 監督:ジュリアン・ デュヴィヴィエ) *「レベッカ」(40)は、ヒッチコックがアメリカに渡って撮った最初の作品。ローレンス・オリビエとジョーン・フォンティン主演。格調高い恋愛映画として見てもよく出来ているが、フォンティンが姿のないレベッカの亡霊におびえる辺りの描写はさすがヒッチコック。コワい家政婦役を演じたジュディス・アンダーソンもうまい。アカデミー作品賞を獲得したがヒッチは監督賞を取れず仕舞。 *同じくヒッチコックの「海外特派員」(40)は、第2次大戦に突入しつつある時代の空気を巧妙に取り入れ、政治サスペンス映画としては一級品。次から次へと息もつかせぬ展開で、ヒッチの本領発揮。風車小屋のサスペンスなど、見どころも多い。もう少しでベスト入り。 |
| 17 |
「チャップリンの独裁者」 ('40) 米/監督:チャールズ・チャップリン チャップリンはつくづく天才だと思う。1940年といえば、ヨーロッパで戦線が拡大しているとは言え、まだアメリカは参戦しておらず、また戦争の趨勢も定まっていない時。この微妙な時期にヒットラーを徹底的にからかった作品をよく作ったものである。ちなみに日本は同じ時期、日独伊三国同盟を結び、ヒットラーに手を貸していた…。優れた芸術家はまた、優れた預言者であるのかも知れない。 |
小林さんのベスト100: (29)「フィラデルフィア物語」 ('40 監督:ジョージ・ キューカー) (30)「ヒズ・ガール・フライデー」 ('40 監督:ハワード・ホークス) (31)「桃色(ピンク)の店」 ('40 監督:エルンスト・ ルビッチ) (32)「哀愁」 ('40 監督:マーヴィン・ルロイ) (33)「ミュンヘンへの夜行列車」 ('40 監督:キャロル・リード) *「怒りの葡萄」(40)。スタインベックの同名小説をジョン・フォードが監督。'30年代、凶作にあえぐ農民たちの視点から搾取する資本家側を糾弾するという骨太のテーマの力作。ヘンリー・フォンダが好演。ストのリーダーを殺した男を殴り殺したことからフォンダは逃亡の旅に出る。母(ジェーン・ダーウェル)との別れ際にフォンダが語るモノローグがとても感動的。アカデミー監督賞と助演女優賞(ジェーン・ダーウェル)を受賞。わが国では戦後も永らく公開されず、やっと'63年に初公開。それにしてもこういう作品を大作としてこしらえ、それにアカデミー賞を与えるアメリカという国の懐の広さには感心。 |
| 18 |
「市民ケーン」 ('41) 米/監督:オーソン・ウェルズ
|
双葉さんのベスト100:
(39)「わが谷は緑なりき」 ('41 監督:ジョン・フォード) (40)「偽りの花園」 ('41 監督:ウィリアム・ワイラー) 小林さんのベスト100: (34)「市民ケーン」 (左参照) (35)「レディ・イヴ」 ('44 監督:プレストン・ スタージェス) *ヒッチコックの「断崖」(41)は、夫(ケーリー・グラント)が殺人犯ではないかという妄想に取り付かれた妻(ジョーン・フォンティン)の疑惑(これが原題)を描いた秀作。いかにも怪しい(?)グラントは本当に殺人者なのか…という展開がスリリングで見応えあり。ラストは実は原作とは180度違っている。わが国では戦後に公開され、'47年度のキネマ旬報ベストワンを獲得。 *この時代のヒッチコック作品をあと2本。「逃走迷路」(42)はおなじみ、無実の罪を着せられた主人公が真犯人を追うストーリー。戦争中という事もあり、反ナチ的な色合いが濃い作品だが、主役が馴染がないし展開もモタつき気味で出来はいま一つ。しかしラストの自由の女神像のぶら下がりサスペンスはさすがヒッチコック。戦争中にしては合成特撮はよく出来ている。 「疑惑の影」(42)は、叔父(ジョセフ・コットン)が殺人犯人ではないかと疑う少女(テレサ・ライト)の心理描写が秀逸。サスペンスの盛り上げ方はこの時代一番ではないか。前作と違い、戦争の影はまったくなし。何度見ても面白い。 *ハンフリー・ボガート主演のハードボイルドの傑作「マルタの鷹」(41)も面白い。監督はジョン・ヒューストン。これがデビュー作とは思えない引き締まった演出を見せる。 *「誰が為に鐘は鳴る」(43)。ヘミングウェイ原作。サム・ウッド監督。スペイン動乱に参加したアメリカ人のゲーリー・クーパーと、そこで会ったゲリラのジプシー娘イングリッド・バーグマンとの短く燃えた恋を描く。カラー作品だがやや色がどぎつい。バーグマンが美しい。ラストの別れは泣けます。 |
| 19 |
「カサブランカ」 ('42) 米/監督:マイケル・カーティス
|
双葉さんのベスト100:
(41)「疑惑の影」 ('42 監督:アルフレッド・ ヒッチコック) (42)「ヘンリイ五世」 ('44 監督:ローレンス・ オリヴィエ) 小林さんのベスト100: (36)「カサブランカ」 (左参照) (37)「運命の饗宴」 ('42 監督:ジュリアン・ デュヴィヴィエ) (38)「モロッコへの道」 ('42 監督:デヴィッド・ バトラー) *「毒薬と老嬢」(44)。フランク・キャプラ監督としては珍しいブラック・コメディの快作。身寄りのない老人を片っ端から毒殺する事が本人の為と思い込んでいる頭のおかしい老婦人の周りで起きるドタバタ。ケーリー・グラント、ピーター・ローレ、レイモンド・マッセイと役者も揃っている。元は舞台劇だが、脚色を担当したのが「カサブランカ」のジュリアス・J・エプスタインとフィリップ・G・エプスタインのコンビであるというのも面白い。 |
| 20 |
「天井桟敷の人々」 ('45) 仏/監督:マルセル・カルネ 前後篇二部に別れた、3時間15分もある大作。これがナチス・ドイツの占領時代=1943年から2年間もかけて製作された作品であるというから驚く。しかも戦意高揚的部分もなく、ただ多彩な登場人物たちが織り成す恋愛模様をゆったりとした時間の流れの中で描いているだけである。“占領されていても、これだけ堂々とした芸術を作る余裕も力もあるんだぞ”と主張しているわけで、前項の「カサブランカ」の中で、ドイツ軍兵士達が歌う「ラインの護り」に対抗してフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」を歌いだす、あの心意気に通じるものがある。わが国だったら戦争中にこういう恋愛映画など絶対に作らせなかっただろうと思うと、フランスという国の心の豊かさ、芸術を愛する勇気に敬意を表したいと思う。 |
双葉さんのベスト100:
(43)「逢びき」 ('45 監督:デヴィッド・リーン) (44)「陽気な幽霊」 ('45 監督:デヴィッド・リーン) (45)「天国と地獄」 ('45 監督:ブルース・ ハンバーストーン) (46)「天井桟敷の人々」 (左参照) 小林さんのベスト100: (39)「乙女の星」 ('45 監督:クロード・ オータン・ララ) *ヒッチコックの「救命艇」(44)は狭いボートの中だけで展開する、一種の密室劇。ヒッチがどこに登場するかは見てのお楽しみ。ただし劇場未公開。 |